つい最近、NPO協力のもと、公立小学校で似たような授業が行われたというニュースを見た。
260日かけてヒラメを育て、最後に食べるか海に逃すかを話し合うというものだ。
クラスにヒラメの稚魚が運ばれてきた時、主催者のNPO代表理事はこのように児童に伝えた。
「この瞬間から、みんなにはヒラメのお父さん・お母さんになってもらいます」
この授業でも最後、多数決で食べることが決まり、児童の前でヒラメを○して、食べるというものだった。
学校の調理室のような無機質な場所で、割烹着を着た調理人がヒラメを包丁でしめる。
合掌しながら号泣する女の子が映し出され、その後はグループに分かれて、しゃぶしゃぶにして食べるようだ。
ここでも感受性の高い女の子は、食べてはいけないもの、嫌なものを食べるような顔で涙を流しながらヒラメを口に運んでいた。
「子どもの頃から議論を積み重ねることは、環境問題の解決に重要」
児童とは対照的に、誇らしげな顔で語る大人が映し出された。
価値注入型の授業
金太郎飴(あめ)のような感想文
教員時代に、道徳の授業で映画を見て生徒に感想文を書いてもらった。
すると、以下のような教師が求めるような答えを予測したかのような意見や感想が出てくる。
「●●は、知らなかったので知れてよかった」
「これからは気をつけていきたい」
「命の大切さを知った」
「これからは差別しないように気をつけたい」
仮説検証をして、最後の価値判断は児童・生徒に任せるという手法は、模擬投票や模擬裁判など社会科の授業でやったことがある。
しかし、多くの道徳の授業のやり方が、価値注入型であり、価値観や道徳観の押し付けになっているような気がしてならない。
命の尊さを学ぶ授業と称して動物に名前をつけ、世話をし、議論はするが、最終的には殺してしまう。
そして「命の尊さを知ることができた」という児童・生徒の感想が出るところまで脚本があるようである。
どの授業でも共通して最初、動物に名前をつけることから始まり、観察して餌をやり、一緒に遊んだりする。
畜産を生業とする人たちは、動物に名前や相性をつけたとしても、最後は○して食べるという覚悟を持って動物と接している。
逆に、最後は美味しく食べてもらうために、できる限りのことをする。
○すか○さないかもわからないのに、名前をつけたり、一緒に遊んだりすることは、ペットのように単に感情移入させるためのものに他ならない。
○して食べる以外の選択肢は実行されないのだろうか。
そこに最大の疑問を感じる。
表現の自由が保障された民主主義社会において、なぜすべて同じ結末になるのだろうか。
やはり、教師や教育委員会の考えるシナリオがあるのだろうか。
例えば、多数決で負けたが、実家がお金持ちの児童・生徒の家で豚が余生を送ることになった。
「食べない」に投票した児童は、泣いてまで無理やり食べなくてもいいのではないか。
多数派の意見に強制的に従わされて、食べることを強要される。
「名前をつけたり、ペットのようにかわいがるのは違うのではないか」
など、さまざまな意見が出てもいいのではないか。
そのような意見が出ないような雰囲気を教師や学校全体が作っているのか。
許されない多様な意見
私が小学校の時、同和関係の映画を見て、自分なりに考え、「後世に伝えなければ、差別がなくなるのではないか」と感想文に書いた。
すると、私だけが担任に呼び出された。
「そんなことでは差別はなくならない。理解することが大切なんだ」と担任に言われた。
その担任は同和問題についてどこまでの理解、知識があったのだろうか、今でも不思議である。
畜産科がある高校で同じような取り組みが行われていたのをYouTubeで見たことがある。
生徒全員が責任を持って1人1羽のニワトリを育てる。
最初から、最後には○して食べるという約束が周知されている。
わかってはいても、毎日世話をすると嫌でも情がわく。
最後は担任の先生が責任を持ってニワトリを○す。
ここまでして、命の尊さを教える授業は成立するのではないだろうか。
命の尊さを教える授業における4つの問題点
覚悟がない
最後は○して食べるということを周知徹底していない。
中途半端に情が移り、その分、最後に余計な悩みで苦しむことになる。
感情移入
名前をつけたり、一緒に遊んだりすることで、不必要に感情移入させようとする意図が見て取れる。
毎日世話をしているだけでも情はわく。
「この瞬間から、みんなにはヒラメのお父さん・お母さんになってもらいます」などという発言は言語道断である。
多数決という議決方法
多数決という議決方法にも疑問を感じる。
民主主義の中で用いられる多数決と言う議決方法だが、少数派の意見は無視されることになる。
たとえそれが僅差で負けたとしてもだ。
その結果、多数派の意見に従い、泣きながらお肉を食べるはめになる。
決まったシナリオ
すでに脚本があるかのように必ず最後は○して食べる。
このような命の尊さを学ぶ授業の結果は、ほぼすべて○して食べると言うものであった。
「大切に育てた命だから感謝して食べたい」という教師が期待していたような発言がセットで出てくることも共通している。
畜産関係とは無縁で、心の準備ができていない児童の前に、いきなり豚を連れてきて、世話をさせて、さんざん悩ませたあげく、最後は食肉処理センターに送ってしまう。
結局、教師はなにも手を汚さずに、命を尊さを教えた気になるという自己満足に思えて仕方がない。
では教師が問題を起こした時、同様にクラスで多数決を取り、罷免するかどうかを決めてはどうか。
本当に慕われている教師なら多数決をしても大丈夫だろう。
僅差で負けたとしても、多数決という議決方法を思い知ればいい。
不祥事があれば学校全体で隠蔽をはかる。
動物の命は教師の身分より軽いのだ。
思考停止した教師
あれからタブー視されている「被差別部落」「屠場」「猟奇殺人」「障がい者」「性風俗」など、社会学のなかでもアウトローな部分を専門書を買ったりして勉強した。
興味を持って、母校がある京都の出町柳まで、「ある精肉店のはなし」というドキュメンタリー映画を見に行った。
屠場を研究すると、本当に命の尊さがわかるプロだからこそ、少しでも苦しまずに屠○する方法を追求し、肉や皮を無駄にしないために、皮をはぐ技術や刃物などの道具にもこだわりを持つことがわかった。
小学校の時の担任は、なにをもって理解と言っていたのだろう。
教職課程の授業や教職員研修で知りえた知識のみをもって理解としていたのだろうか。
現在では少なくなったが、30年前までは給食を完食することも食育の一つとされた。
好き嫌いをしないで、残さずに食べる。
「もったいない」という言葉があるように、アフリカにいる恵まれない子どもたちのことを考えろという。
現在のアフリカは想像以上に発展している。
教師の固定観念にあるアフリカ像は、どこで止まっているのだろうか。
ダウンタウンの松本人志氏は、「その子らも腹いっぱいになったら残すわ!」と言っている。
飽食の時代になり、SDGsの観点からフードロスなどの問題を考えていかないといけないのは確かである。
しかし、令和になっても食育指導のもと、教師が無理やり給食を児童の口に押し込み、嘔吐したとうニュースを見ると、ゾッとする。
私を休職に追い込んだ学校長は「人権、人権」と口うるさく言っていた。
在日朝鮮人問題や同和問題など、人権にうるさかった。
しかし、教職員の人権には興味がなかったのだろうか。
「灯台もと暗し」という言葉があるように、世界平和を声高に叫ぶ前に、まずは家族や隣人のために必要な事はできているのだろうかと自問自答することである。
地に足ついていないとはまさにこのことだろう。
世界平和や人権と理想をかかげることは大切だが、富士山登頂もまずは登山口にたどり着くことが先決である。
命の尊さを学ぶには
話を戻すが、果たして命の尊さは、公の場で感情移入した動物を○して食べることでしか学べないのだろうか。
「死」はとても身近なものである。
特に自然に出れば「死」は当然のものとしてそこにある。
暑さで干からびたミミズ、短い夏を終えたセミ、身内の不幸など、いくらでも学べる事例はある。
小さい子供に亡くなったおばあちゃんのことをうやむやにするのではなく、「死」について話し合えばいい。
5歳の息子が虫取りでダンゴムシを捕まえ、家で飼うことになった。
彼なりにダンゴムシは、落ち葉を食べるということで、虫かごに落ち葉を1枚入れた。
ダンゴムシものどが渇くかもしれないといって、水を数滴入れた。
1日経つとダンゴムシは死んでしまった。
なぜ死んでしまったのかを息子と話し合った。
土がないからかな、草むらとは環境が違うからかな、息子なりにいろいろ考えた。
たくさん落ち葉を食べられるようにと、落ち葉と一緒にダンゴムシを埋めに行った。
これは息子が自発的にダンゴムシの死と向き合って出した答えだ。
小さな身近な死に向き合うことで、命の尊さを学ぶことができるのではないか。
逆に、子どもがアリを踏んづけている時、「やめなさい」と注意して、子どもの好奇心を制限してしまう。
踏んだらどうなるだろうか、足が取れてしまった。子どもなりの仮説検証ができないまま、大きくなってしまうと、小動物を殺してみたり、猟奇的な殺人につながることもある。
私が小さい頃は、自然が多い母の実家で育った。虫取りもしたし、カエルやヘビ、ハトまで捕まえた。意図せず虫の足が取れてしまったり、捕まえたヘビが死んでしまうこともあった。
自然のなかで生き物から命の尊さについて学んだ。
人を殺してはいけないという事は自明のことである。そのことに説明は不要だ。
いちいち説明を求める人がいるが、理由なんてないことも多い。
街に石があるとつまづくかもしれないので邪魔だというが、登山の途中で石があっても不思議ではない。
都会では、意味あるものしか置かれておらず、「死」を含めた自然は排除される。都会では大きな石は漬物石に便利だと「意味」をつける。
生きることに意味はいらない。
生かされている。生きたくても生きることができない、死にたくても死ぬことができない。だから生かされているという。
そして「生・老・病・死」を恐れずに受け入れなければいけない。昔の人はそれを「覚悟」と言ったと養老孟子氏は説いている。
確かに近代化、都市化のなかで「死」というものが遠い存在になった。
そこで命の尊さを教える重要性が一段と大きくなった。
公の場に動物を連れてきて、名前をつけ、世話をし、議論をして、最後には○してしまう。
それで命の尊さを知ることができたというのではなく、自然やもっと身近なところに命の尊さを学べる方法はあるのではないか。
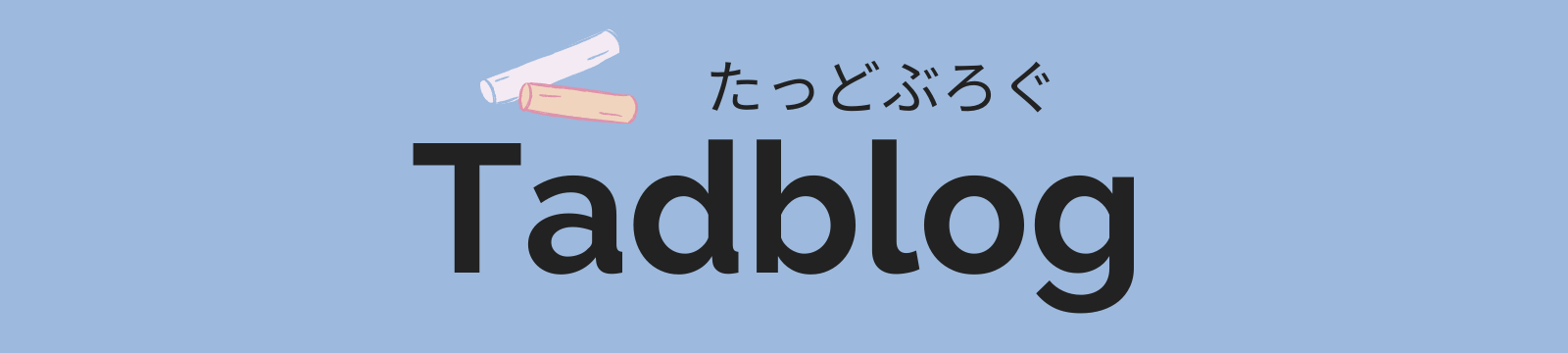


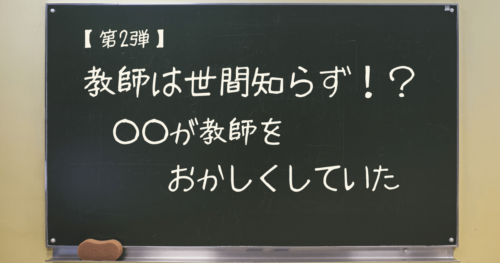
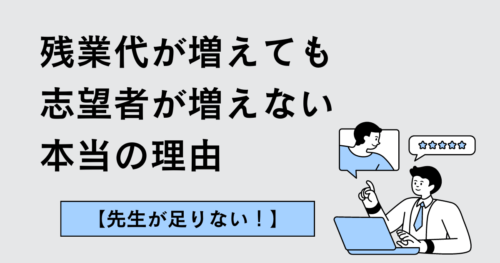
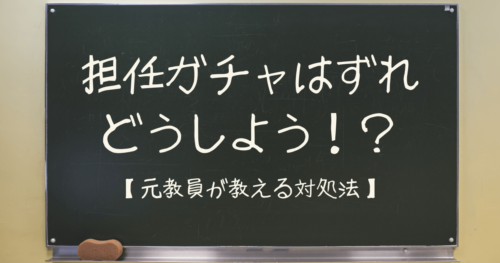


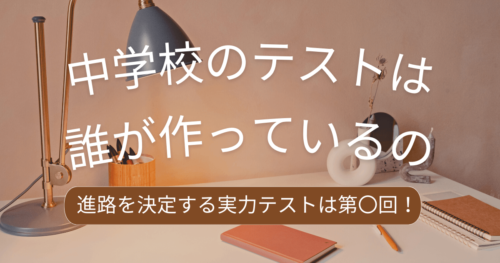


コメント