 心配ママ
心配ママ内申点を上げるためにはどうすれば?
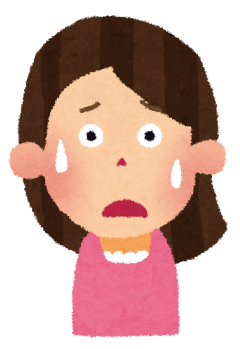
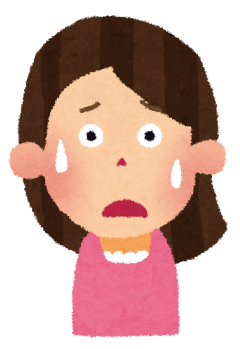
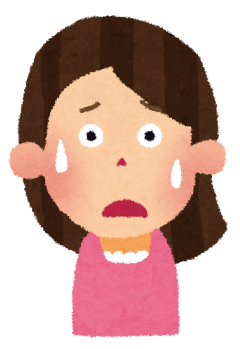
内申書って一体なにが書かれているの?



委員会や生徒会に入っていれば内申点は上がるの?
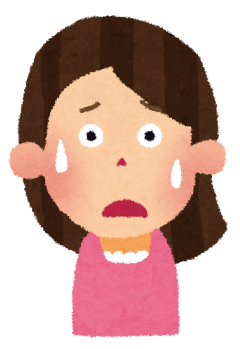
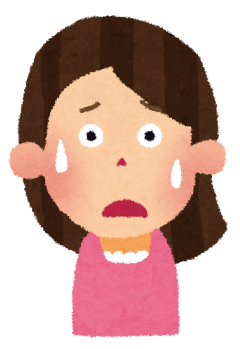
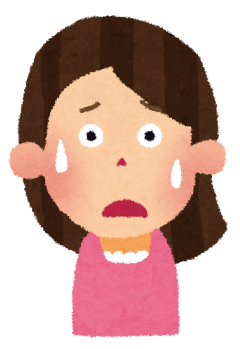
具体的な内申点を上げる方法を知りたい。



任せてください!
この記事を開かれた方は、来年に高校受験を控えた中学3年生か、その保護者かと思います。
また、早くから内申書のことを知っておきたいという熱心な1・2年生もいるかもしれませんね。
この記事では、元公立中学校教員のタッド先生が、以下のことについて丁寧に解説します。
内申書には、どんなことが書かれているのか
部活動や委員会、生徒会の影響
高校入試での内申書の使われ方
内申点を上げる方法
そもそも内申書とは
内申書
内申書は、調査書とも呼ばれ、国公立高校受験時の判定に使われます。
通知表は、学年ごとの各学期の評定が書かれた書類で、懇談で目にするものです。
評定は各教科5段階で、絶対評価によって判定されます。
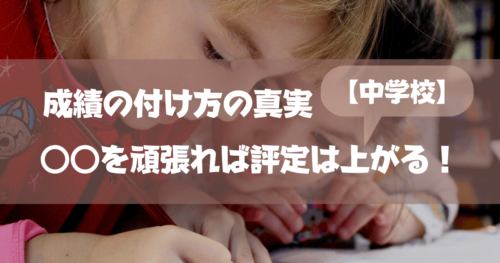
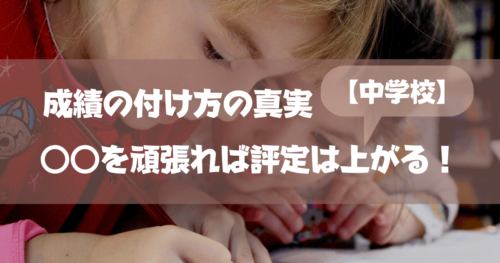
内申点
内申点は、各教科5点×9教科の点数で、「3年生の点数のみ」や「1~3年生すべて」など都道府県によって異なります。



各都道府県の教育委員会のホームページで調べてみてください。
ちなみに大阪府の場合は、1~3年生まですべてが入ります。
さらに比率が違うのです。
中1:中2:中3=1:1:3
3年生の成績は、1・2年生に比べて3倍の重みがあるのです。
内申書には何が書かれているの?
内申書の内容は大きく4つに分かれています。
これも都道府県によって多少異なります。
ここでも大阪府を例に説明します。
1:名前や性別などの基本情報
2:教科の学習の記録
3:出欠の記録
4:活動・行動の記録
1:名前や性別などの基本情報
そのままです。氏名と性別です。
2:教科の学習の記録
9教科の3学期の評定が3年間分書かれています。
通知表を3年分まとめたものと考えてください。
3:出欠の記録
各学年での出欠数が書かれます。
私学の推薦入試の場合、あまり遅刻や欠席が多いと良い影響がありません。
4:活動・行動の記録
「活動/行動の記録」は、記載内容を総合的に評価する観点から欄を一つとし、教科、総合的な学習の時間、特別活動、部活動、その他校内での日常生活を含む中学校での教育活動全般における活動及び行動の記録を、具体的事実を示して記載する。
大阪府教育委員会
生徒会活動や図書委員・国語係などの学級活動、部活動を含む中学校生活全体のまとめです。
大阪府の国公立高校の受験時、ボーダーゾーンにいる生徒のなかから、その高校のアドミッションポリシーに最も適合する生徒を優先的に合格させることになっています。
アドミッションポリシーとは、学校が求める生徒像のことです。
例えば桜塚高校の場合、下記のようになっています。
本校は、地域に貢献し世界を舞台に活躍する人材の育成をめざしています。そのために、
様々な取組を通じて生徒の学ぶ意欲を向上させ、確かな学力を身につけ、知・徳・体のバラ
ンスのとれた人間性を育み、人間力を培っています。そして、地域連携や国際交流を行い、
広い視野を持ったグローバルリーダーを育成することを目標としています。本校の特色を理
解して、高い志と夢を実現するための努力を惜しまない生徒を求めます。
1) 本校に入学したい意志が強く、入学後は自らの進路実現に向けて、高い目標を持って日々
切磋琢磨し、努力を継続できる生徒
2) 本校の専門コース制を理解し、将来的に国際社会で活躍するグローバルリーダーになる
意欲を強く持つ生徒
3) 規則正しい生活ができ、学習を中心として、学校行事、地域との交流、部活動等にも積
極的に参加し、常に自分を高めようとする生徒
4) 英語によるコミュニケーション能力を高める努力をし、積極的に資格取得をめざし、国
際交流等に意欲的に取り組む生徒、または理科や数学に関わる事柄について強い興味・
関心があり、ものごとを科学的に考え、論理的に説明しようと努めるとともに、探究活
動を積極的に行う生徒
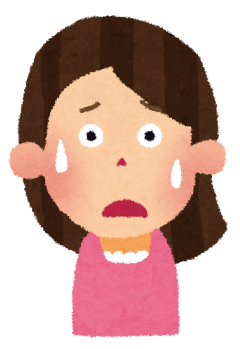
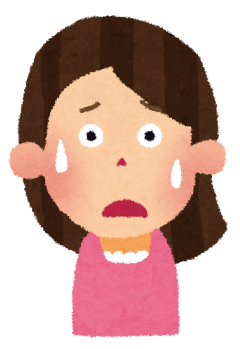
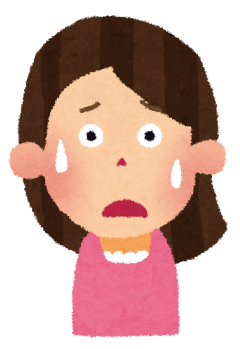
なんだか難しいわ!?
あくまで入試の点数がボーダーゾーンだった時、内申書の「活動/行動の記録」と自己申告書を参考に判定されます。
自己申告書とは、国公立高校を受験する生徒すべてが願書とともに提出しなければいけない書類です。
テーマは、例年10月頃に大阪府教育委員会のホームページで発表されます。
ちなみに令和4年度のテーマです。
あなたは、中学校等の生活 (あるいはこれまでの人生 )でどんな経験をし、何を学びまし たか。また 、それを高等学校でどのように生かしたいと思いますか 。できるだけ具体的に記 述してください。
委員会や部活動は加点されるの?
内申書の大切なところは、「2:教科の学習の記録」と「4:活動・行動の記録」です。
つまり、成績と中学校生活の様子です。
「4:活動・行動の記録」について、教員は悪いことは書きません。
しかし、多少飾りをつけても、ウソを書くことはできません。
部活動をしていなくても、途中でやめたとしてもマイナスにはなりません。
かといって無理に生徒会に立候補する必要もありません。
もちろん、やった方が少しは有利になるかもしれませんが、自分ができる範囲で、委員会活動や日々の学校生活を充実させるだけで十分です。



やはり成績が一番重要です!
国公立高校の入試での内申点の使われ方
内申点の計算方法
特別選抜
中1の9教科の評定(3学期)の合計×1
中2の9教科の評定(3学期)の合計×1
中3の9教科の評定(3学期)の合計×2
合計225点満点
一般選抜
中1の9教科の評定(3学期)の合計×2
中2の9教科の評定(3学期)の合計×2
中3の9教科の評定(3学期)の合計×6
合計450点満点
当日のテスト
特別選抜:各45点×5教科=225点
一般選抜:各90点×5教科=450点
高校別の内申点の比率
また高校別に入試当日の点数と内申点の比率が異なります。
タイプⅠ~Ⅴまであり、Ⅰが偏差値が高く、Ⅴに向かうに従って低い高校になります。
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 7:3 | 6:4 | 5:5 | 4:6 | 3:7 |
| 高い | ← | 偏差値 | → | 低い |
偏差値が高い高校ほど、当日の実力重視といえます。
逆をいえば、偏差値が低い高校ほど内申点がより重要になってくるのですね。
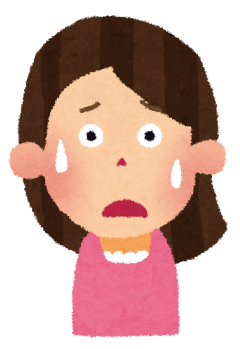
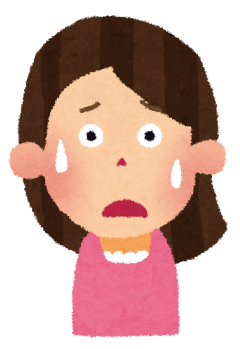
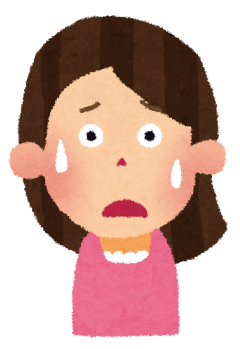
やっぱり内申点は高かった方がいいのね。



じゃあ、どうすれば内申点は上がるの?
内申点の上げ方
内申点が高い方がいいのですが、9教科というところがポイントです。



4教科(副教科)と5教科の割合が同じということに気づかれたでしょうか。
内申点を上げるには、意外と見落としがちな4教科(副教科)が大切なのです。
内申点は3年間の評定を合わせたものです。
評定を上げるって、成績を上げることなのです。
5教科の成績はもちろんですが、4教科(副教科)も同じ割合なのです。



「音楽や美術なんてどうでもいいや」なんて思っていませんか。
もちろん得手不得手があるので、限度はあります。
ただ下手でもいいので提出物は期限までに提出する。
忘れ物や授業態度に気をつける。
4教科(副教科)の定期テストもテスト勉強を頑張る。
上記のようなことであれば、できますよね。
つまり、4教科(副教科)を甘く見ると、内申点が上がらないということです。
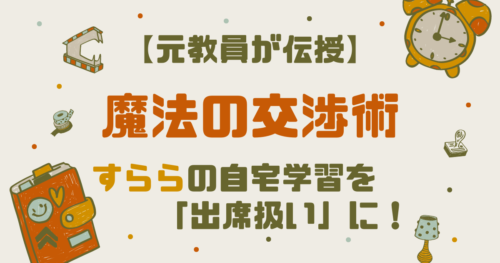
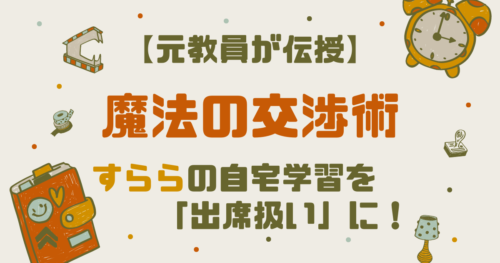
まとめ
いかがだったでしょうか。
内申書は、主に中学校3年分の成績と生活の様子が記載されています。
生活の様子は多少盛ってもウソは書けません。
部活動を途中でやめたからといってマイナスにはなりませんし、生徒会をしたからといってめちゃくちゃ有利になることもありません。
無理をするよりも、日々の授業や部活動など、自分ができる範囲で頑張っていれば問題はありません。
内申点=成績なので、内申点を上げたければ、テストで良い点数を取ることが大切です。
1~3年生までの成績がすべて入り、3年生の成績は3倍の重みがあるので気をつけてください。
特に4教科(副教科)を軽視しがちですが、5教科と同じ比率です。
社会の評定が「3→4」になることと、技術家庭科の評定が「2→3」が同じ価値があるのです。
5教科の勉強は大切ですが、4教科(副教科)での提出物や忘れ物などに気をつけたいですね。
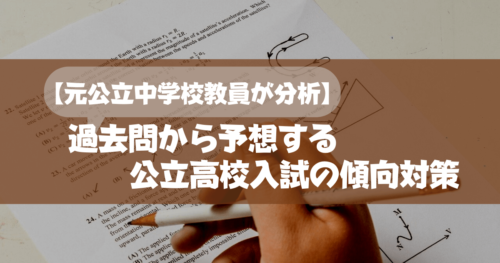
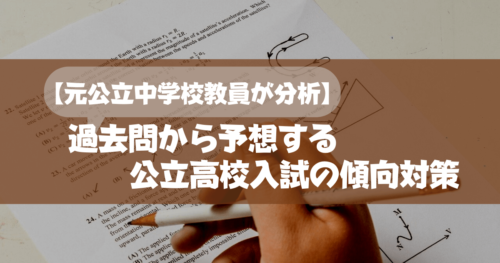
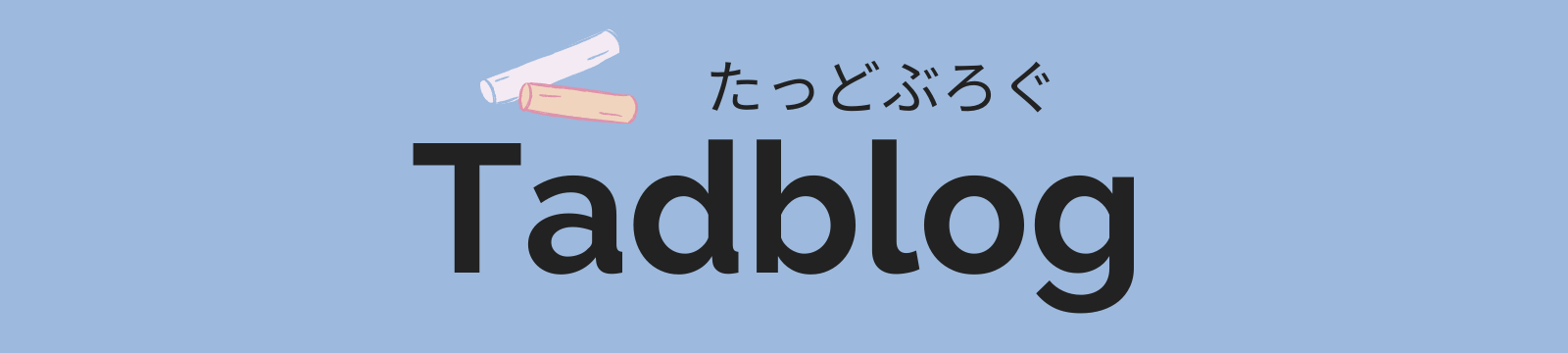
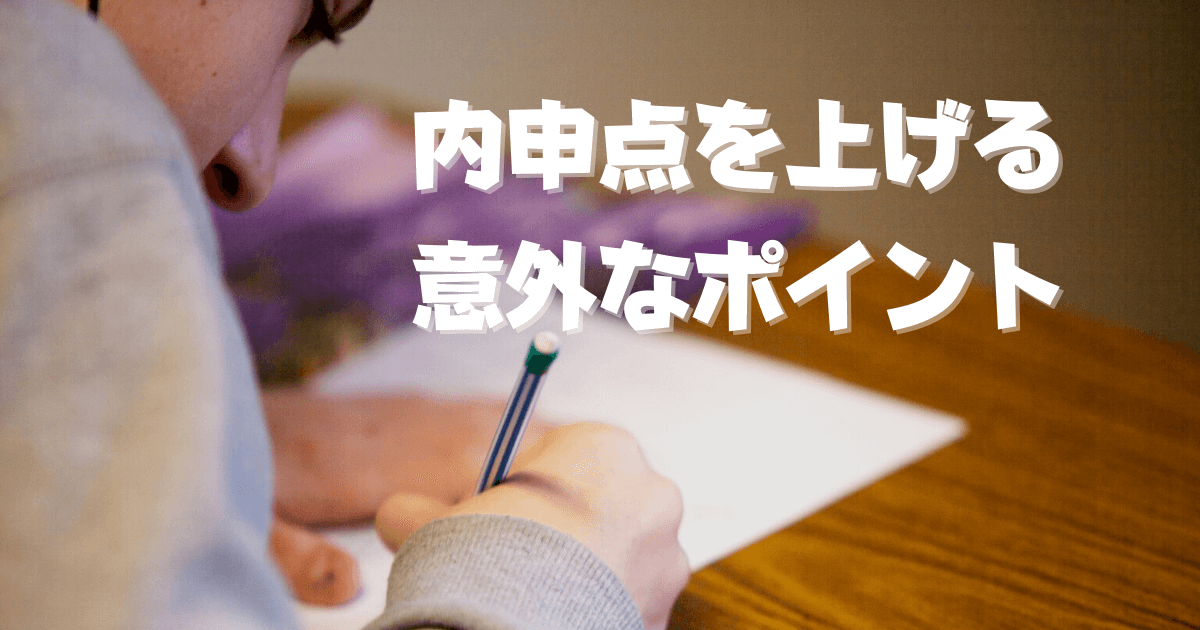


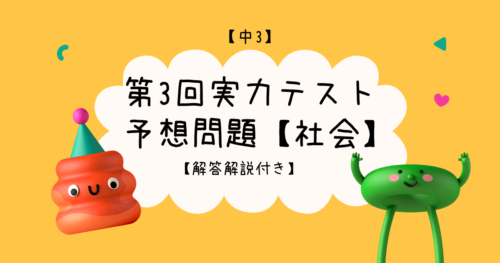
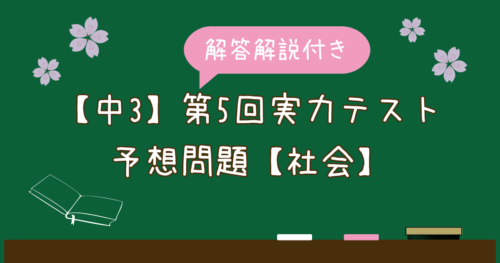
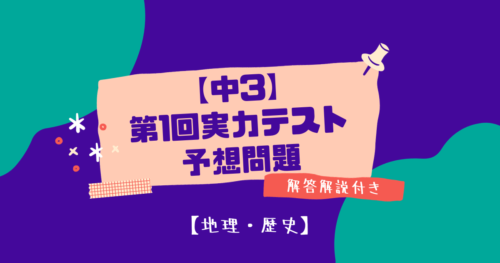
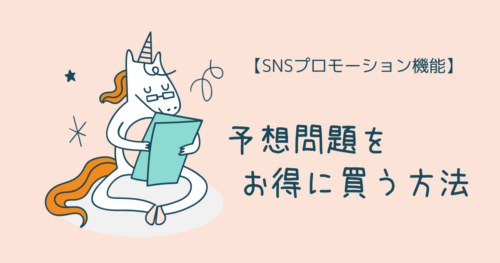
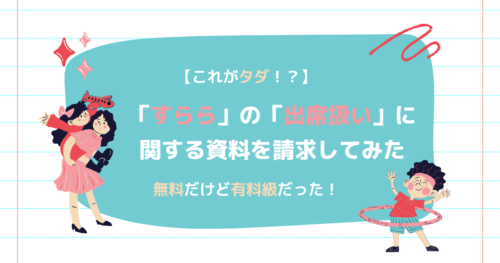
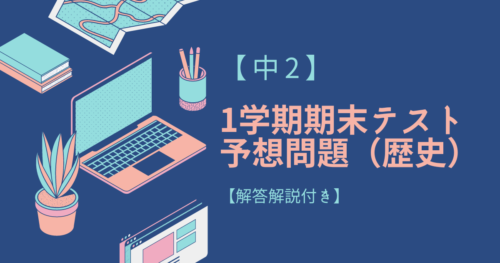
コメント