自慢話はどこか聞き苦しいものですよね。
でも、実は自慢話をしている本人も苦しいのです。
 タッド先生
タッド先生なぜだか分かりますか?
アメリカの臨床心理学者ウェインバーグは、次のように説明しています。
行動は背景にある動機を強化する。



む、むずかしい。
自慢話をする人は、劣等感から虚勢を張ってます。
しかし、自慢話をすればするほど、背景にある劣等感を強めることになるのです。
真の動機は劣等感でした。
またアメリカの刑務所では、このような実験が行われました。
犯罪者をA班とB班の半分に分けて、A班はB班に、いかに犯罪が悪いことかを諭す作業を続けました。するとA班の再犯率が低下したのです。
行動によって背景にある動機が強化されたことがよく分かりました。
これはすべての行動に対していえることで、子育てにおいても当てはまります。
「子どものため」と思った行動の動機が、実は「親自身の不安」であり、やればやるほど親自身の不安を強めていくという悪循環にもなりかねません。
子育ての不安は、子どもがいくつになっても、なくなることはありません。
ただ「世間体」や「偏見」などにしばられた不健全な不安であった場合、必要以上に子どもを苦しめる結果になってしまいます。
この記事では、まさに「世間体」や「偏見」といった不健全な不安にしばられた養育者に育てられた私自身の経験をもとに、子どもの笑顔が増える子育てを考えてみます。
結論からいえば、子育ての悩みは尽きることはありません。
だからといって開き直るのではなく、ピンチこそ立ち止まって考える良い機会なのです。
「休むこと=悪」という私の幼少期
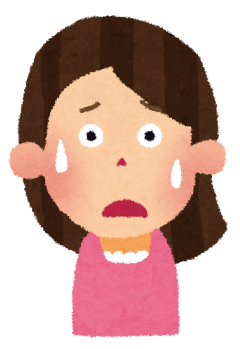
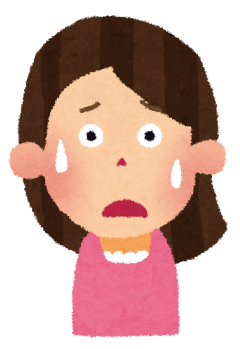
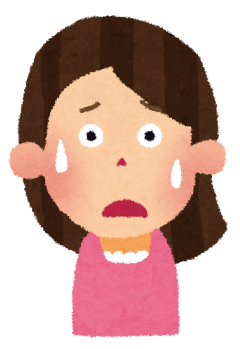
ちゃんと子どもを想ってますよ。



本当にそうなのでしょうか。
幼稚園の遠足で動物園に行った時、スイミングのテストと重なりました。
祖父に「迎えに行って来い」と言われ、母が動物園まで迎えに来たことがありました。



そこまでスイミングのテストは大切なのでしょうか。
また私の祖父は、体調が悪いと言った日であっても、学校を休ませてくれませんでした。
なぜ祖父は学校を休ませてくれなかったのでしょう。
祖父は不安であり、一度休ませると癖になり不登校になるのではないかと恐れていたのです。
祖父の動機は、子どもを想ったことからではなく、祖父自身の不安だったのです。
本当に子どものためだと思うなら、とりあえず休ませてくれたでしょう。



学校は休ませてくれないのに、習い事であるスイミングのテストは大切なんだ。
私は子ども心に、何が大切で何が大切でないかの基準がわからなくなりました。
ただ「学校は休んではいけないものなんだ」という規範意識だけが強くなっていきました。
大人になり、祖父が亡くなった後でも、「休んではいけない」という考えは変わりませんでした。
教員時代、休日に何も予定を入れないことが無駄な時間と思え、教材研究をしたり、自己啓発書を読んだり、なるべく暇を作らないようにしました。
平日の授業に部活動、休日にも部活動や教材研究をして、残った時間にも予定を入れると、体を休める時間がありませんでした。
私の動機は「(不健全な)不安」であり、どんどん予定をこなすことで、さらに不安が強化されていたのです。
まるで海水を飲めば飲むほど、喉がかわくように。
祖父の考え方を内面化、つまり自分の考え方にしてしまっていたのです。
ピンチはチャンス、立ち止まる良い機会



一度立ち止まって考えてみることは、とても大切なことです。
子育てでも自分の人生でも同じです。



行動の背景にある動機はなんなんだろう。
子どものためではなく、親の不安なのではないかと。
繰り返しになりますが、どんな人にも多少の不安はあります。
ここでいう不安は、不健全な不安です。
不健全な不安は、「世間体」と「偏見」が生み出すものと考えます。
「世間体」と「偏見」が生み出す不安は、「~べき」というものが多いです。
「学校には行くべき」
「テストは受けるべき」
「時間は有意義に使うべき」
「正論」ともいえますね。
確かに学校には行った方がいいですが、体調が悪い時は先生でもお休みします。
時間は有意義に使った方がいいけど、大人でもついついダラダラしてしまいます。
この規範意識を子どもに向ける親がいます。
「規範意識」は内ではなく、外へ向けるもので、家庭内には「優しさ」が必要になります。



一体、誰のために学校に行くのでしょうか。
「子どもの将来のため」ではなく、「不登校なんておかしい」という発想や、親自身が近所で合わせる顔がないからではないでしょうか。
まさに子どものためではなく、親のためになっていますね。
ここに気づけば問題は解決に向かっています。
あとは「世間体」と「偏見」を徐々に手放していきましょう。
子育てを例に挙げましたが、自分自身が生きていくうえでも有効です。
特に毒親家庭で育った方は、知らず知らずのうちに毒親の考え方を内面化しています。
「生きづらい」と感じた時が、立ち止まるタイミングです。
日々の行動の動機に着目してみてください。
自分でも他人でもかまいません。
劣等感があるから他人と比較するのであり、比較して劣等感を持つのはない。
加藤諦三氏は、このように述べています。
つまり、動機に劣等感があり、そこから他人との比較が起きています。
劣等感をなくすのではなく、自分は劣等感を持っているのだと気づくことが何より重要です。
子どもの運動会、授業参観に行く。
他の子と比べて足が遅かった。
発表をしなかった。
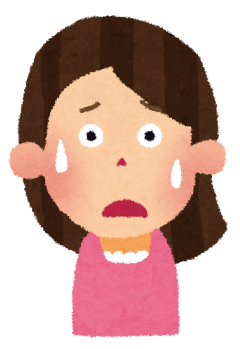
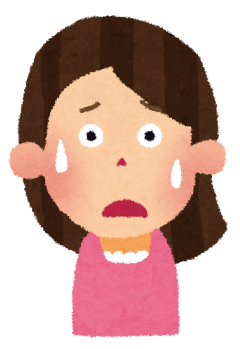
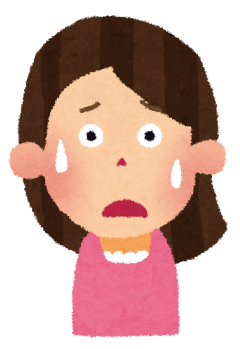
よし、習い事を増やそう!



本当に子どものためでしょうか。
当の本人は大して悔しい、もっと足が速くなりたいなんて思っていないかもしれません。
もっと足が速く、授業でどんどん手を上げて発表して欲しいのは親自身なのです。
子どもは、もっと両親と一緒にいて、遊びたいのかもしれません。
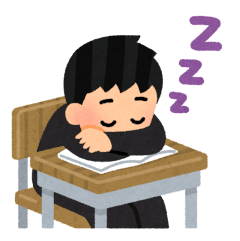
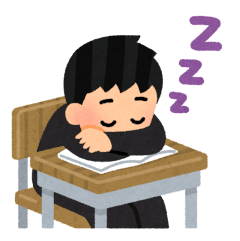
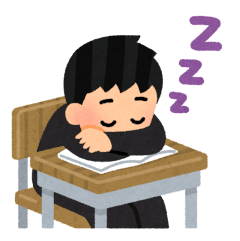
実はさ、今日、学校でこんなことがあってん。
たくさん話を聞いて欲しいのかもしれません。
子どもの本当の願望を理解することが、なにより大切になってきます。
子育てであれば子どもとの対話であり、自分自身の場合は内なる自分との対話です。
真の動機に気づいた時、問題は解決に向かい始めています。
まとめ
瓶のなかに手を入れて、あめ玉を握りしめています。
あめ玉を握りしめている限り、瓶から手は抜けません。
ところが、あめ玉を離せばスッと手が抜けるのです。
ここでいうあめ玉は「執着」といえます。
面白いもので、あめ玉が欲しいと思っている時は手が抜けません。
手放してみようという考えにも至らないのです。
一度、立ち止まり、いつまでもあめ玉にこだわっていると手が抜けないな。
「よし、今回はあめ玉を諦めるか」と思えた時、初めて手が抜けるのです。
あなたが現在、どうしても執着して手放せないものは何ですか。
そこまでしてしがみつかなければいけないものですか。
そして、それは一体誰のためのことなのでしょう。
子どもや自分が本当に欲しいもの、やりたいことは何でしょう。
難しいようで、答えは意外と近くにあるのかもしれません。


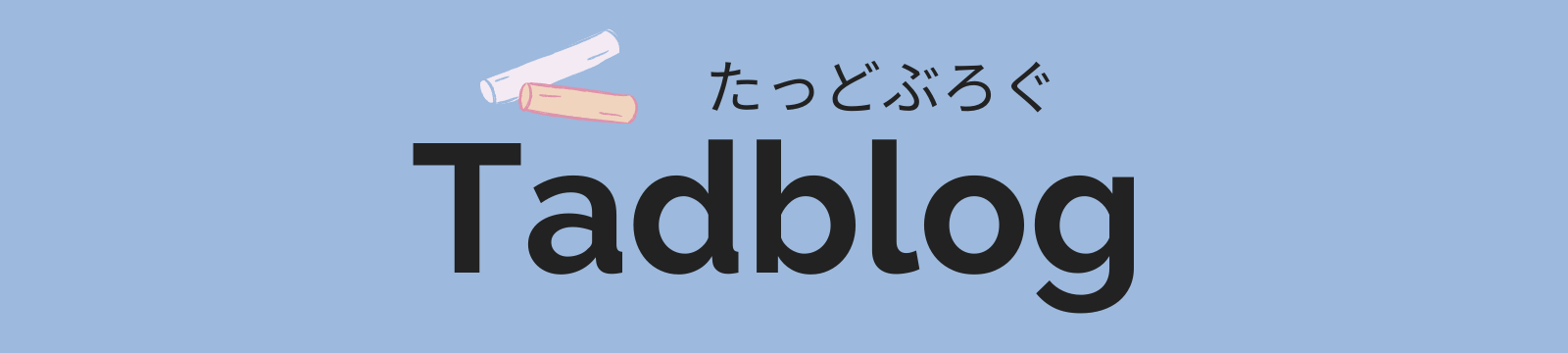

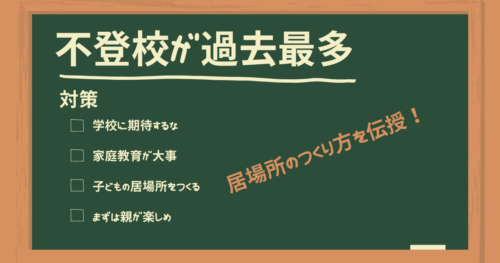
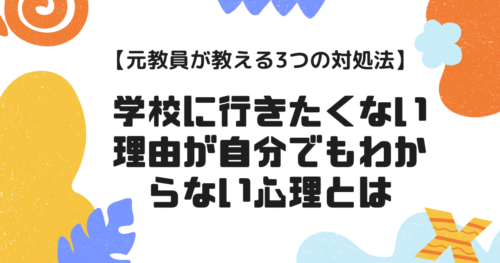
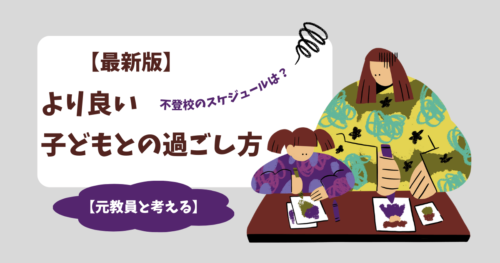

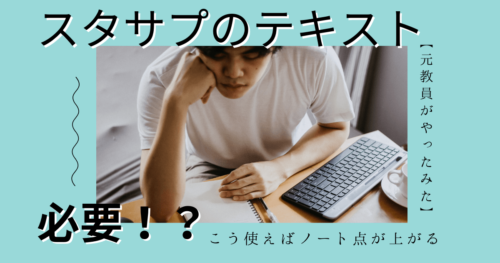

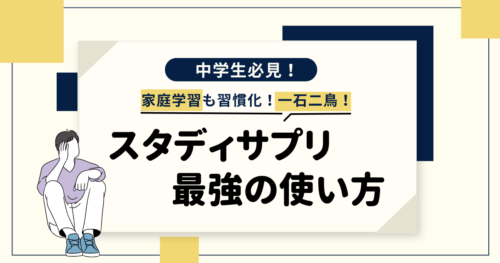
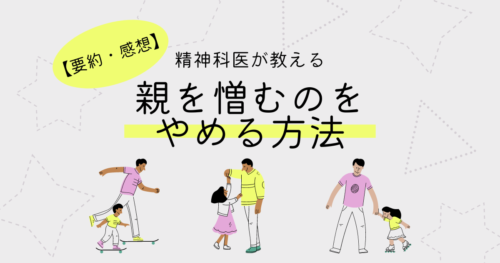
コメント